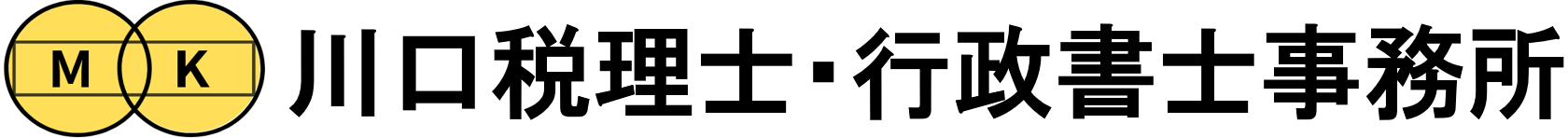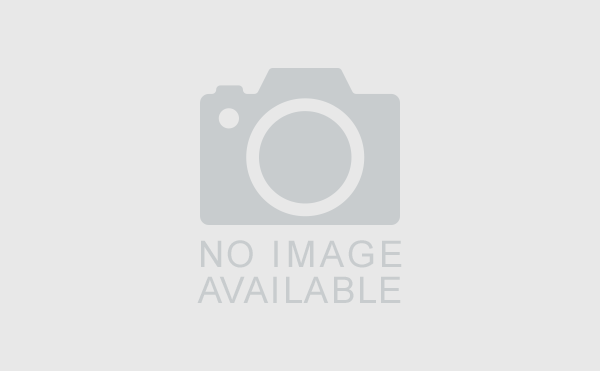取得費の資料がないとどうなる?市街地価格指数で推計された実例
不動産の譲渡所得税を計算するうえで重要なのが 「取得費(いくらで買ったか)」 です。
しかし、購入から長い年月がたつほど、契約書や領収書が残っていないケースは珍しくありません。
今回は、取得費がはっきり分からなかったために、市街地価格指数を使って取得費を推計された実際の事例をご紹介します。
■ 事例の概要
医療法人役員の方が、30年以上前に購入した土地と建物を売却しました。
ところが、
- 売買契約書がない
- 支払先が分かる資料が不足
- 改装費用の証拠も不十分
という状況で、取得費がいくらかが大きな争点となりました。
■ 税務署・審判所はどう計算したのか?
● 1.資料がない部分は「推計」による算定
取得費の実額が分からない場合、税務署は次の方法で計算します。
- 建物:建築単価(統計データ)×面積 − 減価償却
- 土地 :市街地価格指数を使って取得時の価格を推計
ここで出てくるのが 市街地価格指数 です。
■ 市街地価格指数とは?
● 簡単に言うと…
土地価格の値動きを示す指標です。
- 国土交通省の統計に基づき、全国主要都市の地価の変化を数値化
- 特定の地域について、
- 「いつの時点の価格がどれくらいだったか」
を比較できるようにしたものです。
- 「いつの時点の価格がどれくらいだったか」
● なぜ税務で使われるのか?
今回のように、
- 取得時の契約書がない
- 当時の購入価格が証明できない
という場合、税務署は次の考え方をします。
- 譲渡時の売却価格は分かっている
- 建物部分の価額を推計し、それを差し引く
- 残った土地部分の金額に、
取得時と譲渡時の市街地価格指数の比率を掛け戻す
つまり、
「当時のその土地は、今よりどれくらい安かったか?」
を指数で調整して取得時の金額を推計する、というイメージです。
● 具体的にはこんな流れ
土地の取得費 =
(売却時点の土地価額)×
(取得時の市街地価格指数 ÷ 譲渡時の市街地価格指数)
今回の事例では、
- 譲渡時指数:6,826
- 取得時指数:5,241
という数字が使われています。
■ 結果どうなったのか?
- 税務署より多くの取得費が認められたものの、
- 納税者の主張(3,000万円超)までは届かず
- 譲渡所得は一部減額されたが「利益なし」にはならず
つまり、資料不足の影響が大きく残った結果となりました。
■ この事例から分かる重要ポイント
✅ 1.資料がなければ「推計」が避けられない
市街地価格指数は合理的な計算方法として採用されます。
しかしこれはあくまで 実額ではなく“推測値” です。
👉 納税額が思ったより増える可能性があります。
✅ 2.資料があれば“実額”で認められる
逆に、次のような資料が揃っていれば推計は避けられます。
- 売買契約書
- 領収書・振込控え
- リフォームの契約書・請求書
- 通帳で支払先が確認できるもの
資料の有無が税額に直結するという事例です。
■ 将来の売却に備えてできること
- 不動産購入時の書類は長期保管
- リフォーム・建替えの資料も必ず保存
- 古い不動産は資料の整理を早めに
- 相続や事業承継の前に確認しておくと安心
■ ご相談ください
- 昔買った不動産の資料が残っているか不安
- 今後売却・組み換えを検討している
- 相続や事業整理の準備を進めたい
- 「取得費が分からない場合どうなる?」と気になる方
状況に合わせて、最適な対応をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
■ 参考リンク
該当の裁決書はこちらでご覧いただけます:
平成12年11月16日裁決(裁決事例集No.60・208頁) kfs.go.jp