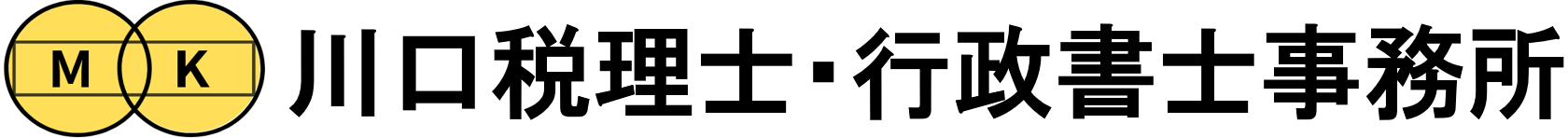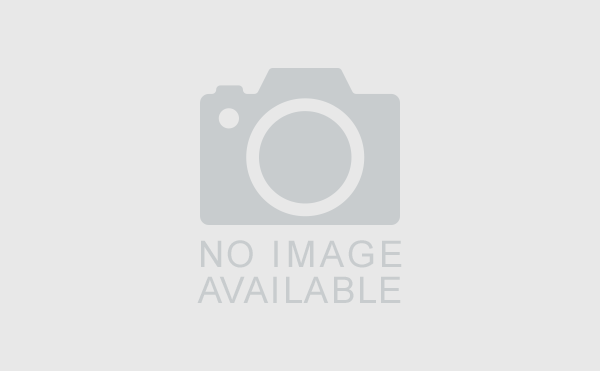ふるさと納税の寄附上限額はこう決める!~住民税の“特例分20%ルール”から逆算する方法~
「ふるさと納税って結局いくらまで寄附していいの?」
「自己負担2,000円で済ませる“ちょうどいい額”を知りたい!」
そんな方に向けて、今回はふるさと納税の**控除上限額の“本質的な考え方”**をお伝えします。
ポイントはずばり、「住民税の特例分」の限度額です。
この数字を基に、寄附額の“損しないライン”を逆算していきましょう。
そもそも控除は3本立て。でも上限を決めるのはココ!
ふるさと納税の控除は、以下の3つで構成されています:
| 種別 | 控除の内容 |
|---|---|
| 所得税分 | 所得控除(確定申告時に一部還付) |
| 住民税・基本分 | 寄附額から2,000円を引いた10%相当 |
| 住民税・特例分 | 残りすべてをまかなう“主役” |
このうち「住民税の特例分」には明確な限度額が設けられており、
✅ 住民税所得割額 × 20%
を超えると、寄附額の一部が控除されず自己負担が2,000円以上に膨らむ可能性が出てきます。
🎯寄附金控除の3本柱(ざっくり図解)
【ふるさと納税の控除】
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃① 所得税 (5~45%) ┃ ← 確定申告で還付
┃② 住民税 基本分(10%)┃ ← 自動控除
┃③ 住民税 特例分 ┃ ← ここがキモ‼
┃ ↑ ┃
┃ これが「20%」まで┃ ← 所得割額の20%が限度
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
💡ここを超えると“控除しきれず”損します!
寄附額の上限を“逆算”する計算式(簡易版)
ふるさと納税の上限額は、次の式で概算できます:
📌 寄附上限額 ≒
住民税所得割額 × 20% ÷(1 − 所得税率 − 10%)+ 2,000円
- 所得税率:課税所得に応じて5~45%(復興税込み)
- 10%:住民税の「基本分」
- 2,000円:ふるさと納税の自己負担部分
【具体例】年収600万円・独身会社員の場合
- 所得税率:約20%(実効税率 20.42%)
- 住民税所得割額:約30万円(源泉徴収票などで確認)
これを上の式に当てはめると…
30万円 × 0.20 ÷(1 − 0.2042 − 0.10)+ 2,000円
= 60,000 ÷ 0.6958 + 2,000
≒ 86,275円
✅ この方のふるさと納税の上限額は、およそ86,000円が目安です。
※もちろん、実際には保険料控除や住宅ローン控除などの影響も加味して微調整が必要です。
所得割額ってどこで確認するの?
住民税の「所得割額」は以下の資料で確認できます:
- サラリーマン:住民税の「特別徴収税額決定通知書」
- 自営業・フリーランス:市区町村からの「納税通知書」
- 源泉徴収票(市区町村民税・道府県民税の明細欄)
実は…年収だけで決めるとズレることも
よくある「年収別の寄附上限目安表」は参考になりますが、
- 配偶者控除や扶養控除
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
などがあると、実際の上限額は下がります。
だからこそ、「住民税所得割 × 20%」から逆算する方法は、シンプルで汎用性が高いのです。
シミュレーションも便利!
とはいえ、いちいち計算が面倒な方は、以下の公式ツールを使ってください👇
📎 総務省「ふるさと納税シミュレーション」
👉 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_zeisei.html
まとめ|上限ラインを守れば、ふるさと納税は最強の節税策!
📌ムダなく得する3ステップ
① 昨年の住民税「所得割額」を確認!
② 所得税率をチェック!
③ 式にあてはめて“上限”を逆算!
👉 寄附しすぎは損!計算してから寄附を!
ふるさと納税は、地方自治体を応援しながら、
- お礼の品を受け取り
- 実質2,000円の負担で
- 所得税+住民税のダブル控除
が受けられる“税制上の裏技”ともいえる制度です。
でも、寄附しすぎて控除枠をオーバーすると、単なる高額寄附になってしまいます…。
ぜひ今回の方法で上限を確認し、ムダなく賢く寄附しましょう!