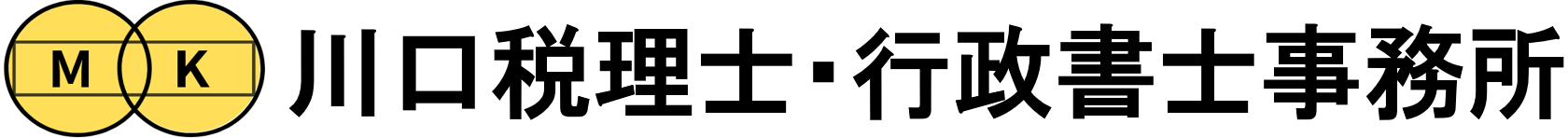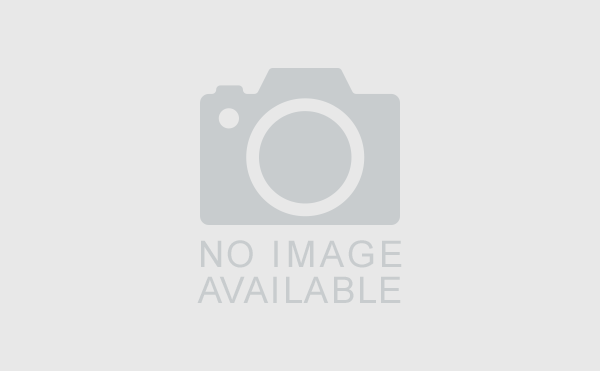生前退職金と死亡退職金の違い
退職金は「働いた最後の報酬」ともいえる大きな財産ですが、課税のされ方が「生前退職金」と「死亡退職金」で大きく異なる点には注意が必要です。
所得税か相続税かの扱いを誤ると、二重課税や申告漏れに繋がる恐れがあります。ここで整理しておきましょう。
1. 生前退職金(退職所得・所得税・住民税)
(1) 課税関係
本人が退職によって受け取る退職金は「退職所得」(所法30条)。
所得税・住民税の課税対象となり、給与所得とは別に分離課税で計算されます。
(2) 計算式
(退職金の額 − 退職所得控除額) × 1/2
※特定役員退職手当等・短期退職手当等の場合は1/2課税の適用制限あり。
退職所得控除額:
- 勤続20年以下 → 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超 → 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
- 障害退職 → 上記に100万円加算
(3) 源泉徴収
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出 → 支払者が所得税・住民税を計算し源泉徴収。原則、確定申告は不要。
- 未提出 → 所得税20.42%+住民税10%相当が一律源泉徴収され、後日確定申告により精算が必要。
👉 ポイント:生前退職金は必ず所得税・住民税が源泉徴収される。
2. 死亡退職金(みなし相続財産・相続税)
(1) 課税関係
被相続人が受け取るはずであった退職金・功労金等で、死亡によって初めて支給が確定したものは「みなし相続財産」(相法3条・12条)。
相続税の課税対象となります。
(2) 非課税枠
500万円 × 法定相続人の数
まで非課税。
- 相続放棄者も人数に算入
- 養子は実子あり:1人まで、実子なし:2人まで
- 相続人以外が受け取った分には非課税枠適用なし
(3) 計算方法(相基通3-31)
相続人の課税対象額は以下で算定します。
各人の受取額 − 非課税限度額 × (各人の受取額 ÷ 相続人全体の受取額)
👉 ポイント:死亡退職金は相続税のみ。所得税・住民税は課税されない。
3. 判定基準 ― 生前退職金か死亡退職金か?
最も重要なのは「支給原因と支給確定の時期」。
- 退職に基づき、生前に支給権利が確定していた → 生前退職金(退職所得課税)
- 死亡によって初めて支給が確定した → 死亡退職金(相続税課税)
判定に迷う典型例
- 退職願提出後に死亡 → 退職日が生前であれば退職所得。死亡により退職となった場合は死亡退職金。
- 定年退職日到来後に死亡 → 定年退職が成立していれば退職所得。ただし死亡退職金として別途支給される功労金等は相続税。
- 業務災害補償金 → 実質的に死亡退職金に準じて相続税課税。
4. 実務上の注意点
- 会社規程・就業規則の確認
支給要件が「退職」か「死亡」かを明確に。 - 支給確定時期の確認
退職日や決議日などの事実確認が必須。 - 二重課税の回避
同一退職金について、所得税と相続税の双方で課税処理しない。
まとめ
- 生前退職金 → 所得税・住民税課税(退職所得控除+1/2課税)
- 死亡退職金 → 相続税課税(非課税枠=500万円 × 法定相続人)
退職金は一見同じ性質のお金に見えますが、「退職によるものか」「死亡によるものか」で税務上の扱いが大きく変わります。実務ではまず支給根拠と確定時期を確認し、適切に判定することが重要です。