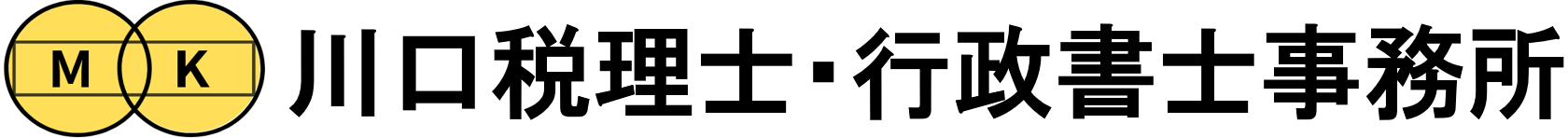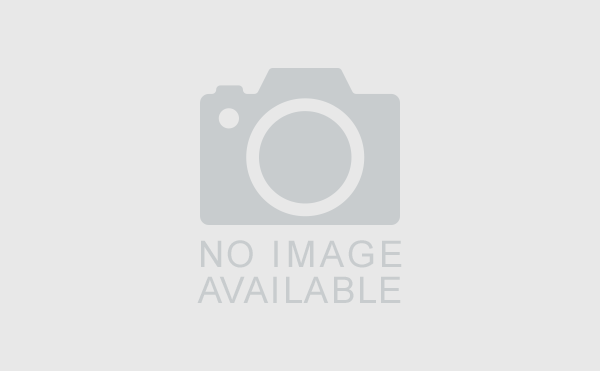親が認知症になったら預金はどうする?成年後見制度と銀行の新ルール
親が認知症になると、預金の引き出しや契約などのお金の管理が難しくなります。このとき役立つのが「成年後見制度」と、2021年に見直された「銀行の一時払戻し制度」です。
成年後見制度(法的に確実に預金を下ろせる方法)
1. 制度の概要
- 認知症や判断能力が低下した人の財産管理や契約を、家庭裁判所が選んだ後見人が代理して行う制度
- 法律で権限が明確に定められており、全国の銀行や役所で通用する唯一の正式な代理方法
2. 後見の種類(判断能力の程度によって選択)
- 後見:ほぼ判断できない状態
- 保佐:判断能力が著しく不十分
- 補助:判断能力が一部不十分
3. 利用の流れ
- 家庭裁判所へ申立て(親族・本人・市町村長など)
- 医師の診断書、戸籍、財産目録などを提出
- 審理(面接や書面確認)
- 後見人選任 → 後見登記 → 銀行で手続き
- 後見人は財産管理・支払い・契約を代行(裁判所へ定期報告)
4. メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 全国どの金融機関でも確実に手続きできる | 申立てに時間(1〜2か月)と費用(数万〜十数万円)がかかる |
| 不正利用防止に強い | 裁判所の監督下で自由度が低い(贈与や資産運用は制限) |
| 長期的な財産管理が可能 | 後見人報酬が発生する場合あり |
2021年の銀行実務指針改正(全国銀行協会)
1. 改正の背景
- 成年後見制度は安全だが、時間と費用がかかるため緊急の支払いに間に合わないケースが多かった
- 認知症の親の入院費・介護費など、急を要する支払いができず生活に支障が出る事例が問題化
2. 改正内容(2021年2月)
- 一定条件のもとで家族による一時的な払戻しを可能に
- 対象となる支払い例:
- 医療費
- 介護費
- 税金や公共料金
- 本人の日常生活費
- 必要書類例:
- 医師の診断書(意思能力がないことの証明)
- 払戻しの目的を示す領収書や請求書
- 家族関係を証明する戸籍謄本など
- 金融機関ごとに上限額や取扱いルールが異なる(例:1回あたり数十万円まで)
3. 限界
- あくまで緊急時の臨時対応で、継続的な引き出しや資産運用は不可
- 手続きは銀行の裁量に委ねられ、対応しない銀行もある
- 書類審査や家族間の同意確認に時間がかかる場合もある
まとめ(使い分けの目安)
| 項目 | 成年後見制度 | 2021年銀行指針の一時払戻し |
|---|---|---|
| 主な目的 | 長期的・包括的な財産管理 | 緊急時の生活費や医療費支払い |
| 権限範囲 | 預金・契約・不動産・全財産管理 | 限定的(医療・介護・生活費など) |
| 手続き期間 | 1〜2か月 | 早ければ数日〜数週間 |
| 費用 | 数万〜十数万円+報酬(場合による) | 無料〜数千円(銀行手数料程度) |
| 有効期間 | 原則、本人が亡くなるまで | 一時的 |
| 銀行での通用度 | 全国統一 | 銀行ごとに判断が異なる |
成年後見制度は、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産管理を行う仕組みで、全国どこでも確実に利用できます。一方で、申立てや報酬などの費用や時間がかかる点がデメリットです。
これに対し銀行の一時払戻し制度は、医療費や介護費といった緊急支出に限り、家族が書類を揃えれば引き出しに応じてもらえる可能性があります。ただし、銀行ごとに対応は異なり、あくまで臨時的な方法です。
長期的な安心を求めるなら成年後見制度を、緊急時の対応には銀行の一時払戻し制度を——状況に応じて使い分けることが大切です。