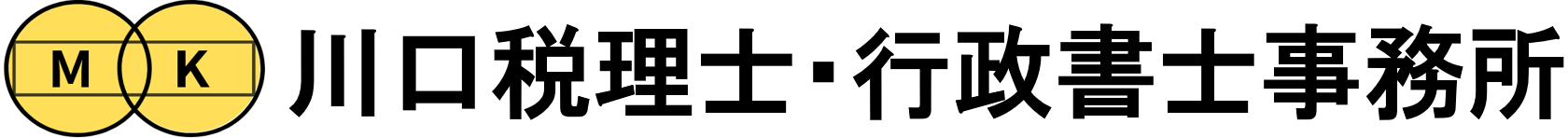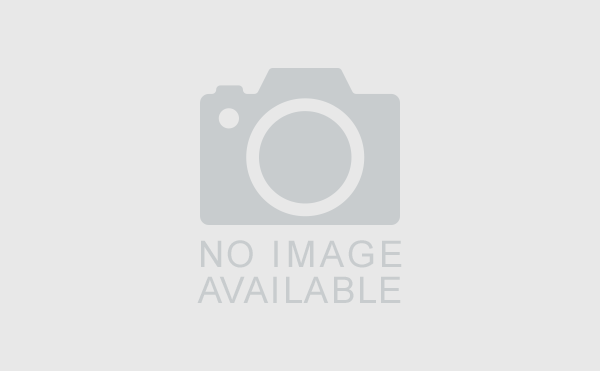令和7年度税制改正のポイント 〜国際課税編〜
グローバル・ミニマム課税の導入と今後の動向
令和7年度の税制改正では、多国籍企業を対象としたグローバル・ミニマム課税の国内法制化が完了しました。これは、年間総収入が7.5億ユーロ(約1,208億円)以上の企業グループを対象に、各国ごとに最低15%の法人税負担を確保するという国際的な取り組みです。
この制度により、国ごとの法人税率引き下げ競争に歯止めがかかり、公平な競争条件の整備やわが国企業の国際競争力の維持・向上が期待されています。
グローバル・ミニマム課税の概要
令和7年度税制改正により、日本では以下の3つの課税ルールが導入・整備されました
- 所得合算ルール(IIR)
親会社が子会社等の税負担が15%に満たない場合、その所得を合算して日本で課税。 - 軽課税所得ルール(UTPR)
他国の親会社が軽課税(15%未満)である場合、日本にある子会社等が代わって課税される仕組み。 - 国内ミニマム課税(QDMTT)
日本にある企業グループ内の事業体の税負担が15%未満の場合、日本で追加的に課税される制度。QDMTTが適用された場合、IIRやUTPRは適用されません。
外国子会社合算税制(CFC税制)の見直し
グローバル・ミニマム課税の導入に伴い、企業の事務負担を軽減する観点から、外国子会社合算税制(CFC税制)についても見直しが行われました。
- 所得合算のタイミングを後ろ倒しに変更
- 申告時に必要な添付書類の範囲を整理・簡素化
なお、グローバル・ミニマム課税とCFC税制は国際的にも並存が認められる制度です。
今後の動向:OECD/G20における国際課税の議論
OECDやG20では、デジタル経済への対応やタックスヘイブン対策を目的として、新たな国際課税ルールに関する議論が続けられています。
国際課税に関する主な課題
- PE(恒久的施設)を持たずに市場に進出する企業の増加
- 法人税の引き下げ競争による税収基盤の弱体化
- 企業間の公平な競争条件の阻害
こうした問題に対応するため、OECDでは「BEPS包括的枠組み」のもと、2本柱の国際課税ルールが提案・整備されています。
まとめ
今回の税制改正により、日本でもグローバル・ミニマム課税が制度化され、国際的な税務環境に対応した制度整備が進んでいます。今後も、OECD等による国際課税ルールの議論が続く中、企業経営や税務戦略には最新の動向を踏まえた対応が不可欠です。